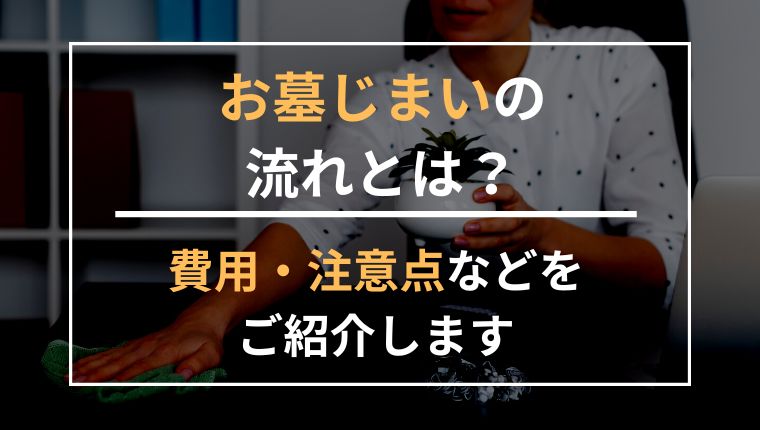
墓終いについてお調べですね?
先祖代々のお墓が遠方にある場合や、今のお墓の後継者がいない場合、これからのお墓の管理方法に悩んでしまうでしょう。
近年では、後継者のいないお墓が荒れ果ててしまったり、墓石が倒壊してしまったりするケースが見られます。
また、今のお墓を残しておくと、子供や孫などに負担となるのでは、と考えてしまう人もいるでしょう。
今回の記事では、墓終いの方法についてお伝えしていきます。
墓終いの費用や、トラブルを避けるための注意点などもお伝えしますので、墓終いで悩んでいる人は是非参考にしてみてください。
ご先祖の供養の方法は多様化していますので、あなたのライフスタイルや考え方に合ったお墓の在り方を見つけましょう。
お墓終いとは?お墓じまいにかかる費用の相場

お墓じまいとは、ご先祖様が建てたお墓を解体して更地に戻し、ご遺骨を別の保管場所に移すことです。
新しいご遺骨の保管には、これまでどおりお墓を建てて供養する方法もありますが、樹木葬や永代供養、納骨堂などを利用して簡略化する場合が多いです。
お墓じまいは、人生で何度も行うことではありませんので、費用がどのくらいかかるのか気になるところですよね。
お墓じまいや費用について、これから詳しくお伝えしていきます。
お墓じまいと永代供養の違いとは?
お墓じまいと永代供養は、行う目的がそれぞれ異なります。
お墓じまいは、ご先祖様が建てたお墓を解体して返還することで、家族が管理や供養をしやすい環境を作るためのものです。
一方で、永代供養は、ご遺骨をお寺や霊園に納骨して、ずっとお寺等で供養してもらうためのものです。
家族で管理が難しいお墓をしまうために、お寺で供養してもらう永代供養を検討するケースも多いです。
なお、永代供養の方法は、それぞれのお寺や霊園によって異なります。
たとえば、他のご遺骨と区別せずにまとめて納骨する合祀型や、お墓と同様に個別に納骨してもらえる個別型などがあります。
合祀型の場合、他のご遺骨と同じ場所に保管するため、ご遺骨の取り出しができなくなる場合が多いです。
永代供養を検討する場合、供養やご遺骨の保管方法について十分確認しておきましょう。
墓終いにかかる費用とは?
墓終いにかかる費用は、30万円~300万円を相場と考えましょう。
費用に大きな差がある理由は、ご遺骨の新しい納骨方法によって費用が大きく変動するからです。
墓終いにかかる費用には、大きく次の2つが挙げられます。
- 今のお墓を解体して更地にする費用 25万円~50万円程度
- ご遺骨を新しく管理する費用 5万円~250万円程度
現在のお墓を解体する工事費だけでなく、ご遺骨を取り出すためにお寺に依頼するお布施や、寺院にお墓がある場合には檀家から離脱するために寺院へ支払う離檀料などがあります。
また、ご遺骨を新しく納骨するための費用もかかります。
たとえば合祀型の永代供養であれば5万円~30万円ほどかかりますが、新たに墓石を購入すると100万円以上かかる場合も珍しくありません。
また、新しく納骨するにあたって寺院に供養を依頼するお布施も必要になります。
墓終いにかかる費用は高額になりがちですので、十分に検討しておきましょう。
墓終いを考えるべき人

費用相場を見ると、「意外と墓終いはお金がかかるな…」と不安を感じてしまうかもしれません。
しかし、お墓の問題を先延ばしにしてしまうと、将来あなたの家族や子供が困ってしまう可能性があります。
次に該当する人は、墓終いについて早めに検討してみましょう。
- お墓を継ぐ人がいない人
- お墓参りが困難になった人
- お墓の維持管理費を抑えたい人
日頃のお墓参りや管理で不便を感じている人は、墓終いについて考えるよい機会です。
墓終いを検討するべき理由について、詳しくお伝えしていきます。
お墓を継ぐ人がいない人
お墓を継ぐ人がいない人は、お墓を維持することが難しいため、墓終いについて考えてみましょう。
将来お墓を管理できる人がいないと、お墓が荒れてしまったり、継承者のいない無縁墓として墓地管理者が墓石を撤去して、他の無縁墓と一緒に祀られる可能性があるからです。
お墓を継ぐ人がおらず、将来的にお墓が荒れ果ててしまうことは、今お墓を管理している人にとっては悲しいことです。
また、無縁墓となることで、近隣のお墓に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
納骨方法には、永代供養や樹木葬など、お墓を継ぐ人がいなくても納骨できる方法もありますので、生前に墓じまいして納骨方法を見直しておきましょう。
お墓参りが困難になった人
お墓参りが困難になった人も、墓終いを検討するべきです。
お墓を継いだ人が実家から離れて生活していると、お墓参りが重い負担となってしまいます。
法事やお盆、年末年始などの節目に、遠方の実家を往復したり、草掃除などお墓の維持管理を行うのは、時間や労力がかかるだけでなく、帰省費用なども必要になります。
たとえば、自宅近くの墓地へご遺骨を改葬したり、都心を中心に普及している納骨堂を利用したりすることを検討するといいでしょう。
お墓参りしやすい環境を整備することで、先祖をより手厚く供養することにもつながるのではないでしょうか。
お墓の維持管理費を抑えたい人
お墓を維持するための費用が負担と感じているなら、墓終いを検討してみましょう。
お墓の維持管理費は、お墓が続く限りずっと支払い続ける必要があるため、今の維持管理費を支払い続けられるか考える必要があります。
お墓の維持管理費を抑えたいと感じたら、永代供養や樹木葬など維持管理費が不要な納骨方法を選べば、費用を抑えることができるでしょう。
また、子供や孫などの次の世代に経済的な負担を残さないことにもつながります。
お墓の維持管理費を抑えたいと感じている人は、一度墓終いを検討してみることをおすすめします。
墓終いを考える際にまず決めること

墓終いを考えたほうがいいケースを見ると、「私も墓終いを検討したほうがいいのかな」と感じたかもしれません。
しかし、墓終いを検討しようと思っても、何から考えたらいいのか分かりづらいものです。
墓終いを考える際には、まずは次の2点を決めておきましょう。
- 墓終いをするのか改葬するのか
- 墓終いの費用を誰が払うか
墓終いを検討するうえで、まずは決めておくべきことについて、詳しくお伝えしていきます。
墓終いをするのか改葬するのか
まずは、墓終いをするのか、改葬するのか、十分に検討しましょう。
墓終いを検討し始めたきっかけによっては、お墓を移動させ管理しやすくする「改葬」によって解決できる場合があるからです。
たとえば、お墓を継ぐ人はいるが実家から離れて暮らしている場合、後継者の自宅の近くにお墓を移動させる「改葬」で解決できるかもしれません。
また、次の世代にお墓の管理で迷惑を掛けたくないと考えている場合であれば、改葬ではなく、お墓じまいを選ぶことになるでしょう。
墓終いと改葬のどちらを選ぶかは、墓終いを検討するきっかけやお墓への考え方によって異なります。
墓終いを検討する際には、家族や親族も交えて、墓終いと改葬のどちらを選ぶか慎重に決めておきましょう。
お墓じまいの費用を誰が払うか
墓終いの費用は、30万円~300万円ほどかかり、決して安い金額ではありません。
墓終いを検討するときは、費用を誰が支払うかきちんと決めておきましょう。
墓終いの費用を誰が払うかについて特に決まりはないため、あいまいなままではトラブルにつながります。
地域の風習などにもよりますが、一般的にはお墓を受け継ぐ人が墓終いの費用を負担することが多いです。
しかし、お伝えしたとおり高額な支払となるため、家族や親族と十分に話し合いをしてください。
相談のうえ、お墓の後継者を含めて複数の親族で費用を出し合うケースも多いのです。
また、今のお墓の管理者が、自分の死後に負担を残さないようにするため、生前に墓終いの費用を準備している場合もあります。
墓終いの費用負担について決まりはないからこそトラブルとなりやすいので、墓終いを考える際には必ず決めておきましょう。
墓終いを行うメリット・デメリット

これまで、次の世代への負担を残さない、お墓の維持管理費を抑えられるなど、墓終いのメリットについて触れてきました。
負担の軽減など墓終いにはメリットがありますが、一方でデメリットもあります。
墓終いを検討するには、メリットとデメリットをしっかり比較し、よりよい選択を行う必要があります。
特に、一度墓終いを行うと、元のお墓に戻すことは難しいため、慎重に検討しなければいけません。
これから、墓終いのメリットとデメリットについてお伝えしていきます。
お墓じまいを行うメリット
墓終いを行うメリットは、次の3つです。
- 子供や孫など、次の世代に負担を残さない
- お墓の維持管理費を抑えることができる
- 後継者がいなくても無縁墓とならずにすむ
永代供養や樹木葬などの納骨方法では、家族が管理するお墓がありませんので、子供や孫などの次の世代に負担を残さずにすみます。
寺院等で供養を行ってもらえるため、後継者がいない人も将来のお墓の不安を解消できるでしょう。
また、お墓を管理するには、墓地管理者への管理料やお墓の清掃修繕費、法要時のお布施など維持管理費がかかります。
維持管理費を抑えられる供養方法を選ぶことで、経済的な負担を軽くできるでしょう。
そして、お墓を受け継ぐ人がいないと、管理がされずにお墓が荒れ果てたり、墓石の倒壊などのリスクもあります。
墓終いをして寺院にご遺骨の供養を任せることで、今の墓地を返還することができます。
お墓じまいを行うデメリット
墓終いを行うデメリットは次の3つです。
- 他の後継者や親族とトラブルになる場合がある
- 墓終いの方法によっては、合祀となりご遺骨を取り出せなくなる
- 離檀料や工事費、新しい供養の費用が高額になる場合がある
年齢層の高い親族には、墓終いに否定的な人が少なくないため、お墓の管理方法を巡って意見が対立したり、トラブルになったりする可能性があります。
他の継承者や親族と、十分に話し合いが必要です。
また、納骨堂や樹木葬、永代供養では、他のご遺骨とまとめて供養する「合祀」を行うことが珍しくありません。
合祀となった場合はご遺骨を取り出せませんので、供養方法についても十分に検討しましょう。
最後に、墓終いの費用は高額になるというデメリットがあります。
墓終いでは、今のお墓を撤去して新たに供養を行います。
寺院にお墓がある場合には檀家を離れるための離檀料や、新しい納骨場所への費用も支払わなければいけません。
墓終いにあたっては、一時的に大きな支出があるため、経済的に負担となる場合が珍しくないのです。
お墓じまいを安く抑える方法

墓終いの大きなデメリットとして、費用負担が大きいとお伝えしました。
しかし、お墓の後継者がいない場合など、墓終いを考える人は多いでしょう。
これからは、墓終いの費用を安く抑える2つの方法をお伝えします。
- お墓を撤去する石材店を決めるときに、複数業者からの見積もりをとる
- 新しい納骨方法の費用を抑える
お墓の撤去工事は、石材店によって費用が大きく異なることも珍しくありません。
複数の業者に見積もりしてもらい、比較することで費用相場を知ることが重要です。
中には、墓石の撤去工事で、相場より高額な料金を請求されたケースもあります。
複数業者に依頼し、現地で見積もりしてもらうことをおすすめします。
また、費用負担の小さい納骨方法を選ぶことで、墓終いの費用を抑えられるでしょう。
樹木葬や永代供養、納骨堂の場合は、5万円程度から利用できる場合もあります。
ただし納骨方法によっては合祀となり、ご遺骨を取り出すことが二度とできない場合があるので、納骨方法を慎重に選びましょう。
お墓じまいを進める7つのステップ

墓終いは、次のとおり進めていくと、スムーズです。
- 親族と相談して同意を得る
- 墓地の管理者に相談をする
- ご遺骨の新しい納骨先を決める
- 墓地所在地の自治体から「改葬許可申請書」を取得
- 閉眼供養・ご遺骨の取り出しを行う
- 墓石を撤去・墓地の返還
- ご遺骨を新しい納骨先に納骨
墓終いでは、するべきことが多く、手順を踏んで手際よく行わなければいけません。
間違った手順で墓終いをしてしまうと、親族間でトラブルになったり、新しい納骨先でスムーズに納骨できない可能性があります。
それぞれのステップについて、詳しくお伝えしていきます。
ステップ①:親族と相談して同意を得る
まずは、墓終いについて親族と相談して同意を得ておきましょう。
相談が不十分であったり、相談せずに墓終いを行ってしまったりすると、親族間でのちにトラブルとなる可能性が高いからです。
たとえば、新しい納骨場所や管理の方法について、十分に話し合ってください。
墓終いは故人の親戚にも関わることですので、普段交友関係の薄い親戚にも同意を得る必要があるでしょう。
また、費用負担を他の親族にもお願いする場合には、墓終いの費用負担についても了承を得る必要があります。
墓終いは家族だけでなく、故人の親族にもかかわることですので、相談のうえ同意を得ておきましょう。
ステップ②:墓地の管理者に相談をする
親族の同意が得られたら、今利用している墓地の管理者に墓終いの相談をしておきます。
墓地が寺院にある場合、墓終いにあたって離檀料が必要となる場合があるからです。
離檀料は、金額は任意の場合もあれば、費用相場がおおよそ決められている場合もあります。
墓終いを始める前に、離檀料の有無や金額について確認しておきましょう。
また、墓終いでは、墓地管理者に埋葬証明書を発行してもらう必要があります。
埋葬証明書とは、現在ご遺骨をお墓に埋葬していることを墓地管理者が証明する書類で、ご遺骨を取り出すための行政手続きに必要です。
墓地の管理者に相談するときに、埋葬証明書の発行についても依頼してください。
なお、相談にあたっては、今まで供養でお世話になったお礼や、墓終いするにあたった経緯などを説明しておくといいでしょう。
ステップ③:ご遺骨の新しい納骨先を決める
親族や墓地管理者への相談が終われば、ご遺骨を納骨する場所を決めましょう。
今のお墓から取り出したご遺骨を勝手に処分することはできないからです。
永代供養や納骨堂の利用、樹木葬など新しい供養方法を決め、新しい納骨先と契約を結んでおきましょう。
また、新しい納骨先から「受入証明書」を発行してもらってください。
受入証明書は、取り出したご遺骨を供養することを新しい納骨先が了承したことの証明です。
受入証明書は、自治体に提出する改葬許可申請書に添付する必要があるため、忘れずに受領しましょう。
ステップ④:墓地所在地の自治体から「改葬許可申請書」を取得
今の墓地がある市区町村で改葬許可申請書を取得し、申請しましょう。
申請後に受領する改葬許可証がなければ、今のお墓からご遺骨を取り出すことができないからです。
改葬許可申請書には、今の墓地管理者が発行した埋葬証明書と、新しい納骨先が発行する受入証明書を添付します。
申請書は、自治体のホームページでダウンロードできる場合もあるので、確認してみてください。
散骨や手元供養の場合、改葬許可証が不要な場合もありますが、自治体によって取り扱いが異なるので確認しておきましょう。
なお、改葬許可証を受け取るまでに1週間ほど掛かる場合もありますので、時間にゆとりをもって申請しておくといいでしょう。
ステップ⑤:閉眼供養・ご遺骨の取り出しを行う
市区町村から改葬許可が出たら、閉眼供養を行い、お墓からご遺骨を取り出しましょう。
お墓にはご先祖や仏様の魂が眠っているため、お墓を撤去する前に、込められた魂を抜く「閉眼供養」を行う必要があると考えられているからです。
改葬する前に、僧侶に閉眼供養を依頼し、お墓の前で読経してもらいましょう。
お供えや塔婆など、閉眼供養で準備しておくものは、宗派や地域によって異なるので、閉眼供養を依頼する寺院に確認しておくといいでしょう。
お布施の金額について明確な基準はありませんが、3万円~10万円程度が目安です。
閉眼供養が終了すると、ご遺骨の取り出しができるようになります。
ご遺骨の取り出しには、重い石をのける必要があるため、石材店にお願いすると安心です。
ステップ⑥:墓石を撤去・墓地の返還
ご遺骨の取り出しが終わったら、墓石を撤去し墓地を返還しましょう。
墓地を管理者に返還するにあたっては、墓石だけでなく、お墓の土台も解体して、更地にしておかなければいけません。
墓石や土台の解体には重機が必要ですので、石材店に依頼して撤去してもらうことが多いです。
ただし、重機の進入路を確保できない山道や狭い道の場合、人力で解体しなければいけないため、費用が高額になりがちです。
事前に石材店に見積もりをしてもらうと、費用の目安を把握できます。
墓終いの費用を抑えるには、複数の石材店から見積もりをとって料金を比較する方法もあるため、検討してみるといいでしょう。
ステップ⑦:ご遺骨を新しい納骨先に納骨
ご遺骨の取り出しが終わったら、新しい納骨先へ納骨します。
まずは、新しい納骨先の管理者に事前に日程を調整しておきましょう。
開眼供養や納骨の準備を行う必要があるからです。
開眼供養とは、新たなお墓や石塔などに魂を込める法要のことで、閉眼供養の逆の意味を持ちます。
納骨先の管理者と相談しながら、住職に開眼供養をお願いしておきましょう。
なお、市区町村が発行した改葬許可証を納骨時に渡す必要がありますので、忘れずに持参してください。
新しい納骨先に納骨が終われば、墓終いの手続きが全て完了します。
お墓じまいを考える際によくある質問

これまで墓終いについてお伝えしてきましたが、墓終いの進め方についてお悩みのことはありませんか?
これからは、墓終いを考えるときによくある疑問に、お答えしていきます。
墓終いを考えている人だけでなく、墓終いの段取りをしていて疑問を感じている人も、是非参考にしてみてください。
お墓じまいに適さない時期やタイミングはある?
墓終いのタイミングに決まりはありません。
ただし、お盆やお彼岸、年末年始などは避けたほうがいいでしょう。
寺院の繁忙期であるお盆やお彼岸は、、閉眼供養や開眼供養を依頼してもすぐに対応してもらいにくいからです。
また、お墓参りをする人が多い時期でもありますので、お墓の撤去や新しく納骨することがスムーズに進みづらいでしょう。
年末年始やお盆など親族が集まる場で墓終いについて親族と話しあい、墓終い自体は寺院の繁忙期を避けて行うことをおすすめします。
お墓じまいで注意するべきことは?
墓終いで注意するべきことは、親族と十分に相談して同意を得ることです。
説明が不十分であったり、同意を得ていなかったりすると、親族間のトラブルに発展する可能性が高いからです。
先祖代々のお墓は、今墓終いを考えている継承者だけの問題ではありません。
お墓に眠っているご先祖の親族にも関わる、大きな問題と言えます。
普段交流のない親族であっても、故人にとっては縁の深い親族にあたる場合もあります。
墓終いをすることを事前に親族とよく相談して、同意を得てから墓終いを進めていきましょう。
お墓じまいの補助金はある?
自治体によっては、墓終いにかかる費用の一部を補助金で補ってくれる場合があります。
管理者のいないお墓をそのままにしておくと、墓石の倒壊など様々なリスクがあるため、自治体としても避けたいからです。
自治体によっては、墓石の撤去工事費や、新たな納骨先への支払など、墓終いで必要になる費用の一部を対象としています。
ただし、墓終いを対象とした補助金制度は、まだそれほど普及しておらず、実施している自治体は少ないのが現状です。
まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。
墓終いの補助金制度が無くても、倒壊の恐れがあるお墓の修繕費の助成など、利用できる制度をアドバイスしてくれる可能性があります。

監修者AOAO研究員(すーさん)
これまでブルークリーン㈱で数々の特殊清掃や遺品整理などを見てきた経験から、
AOAOで記事の監修を行っています。