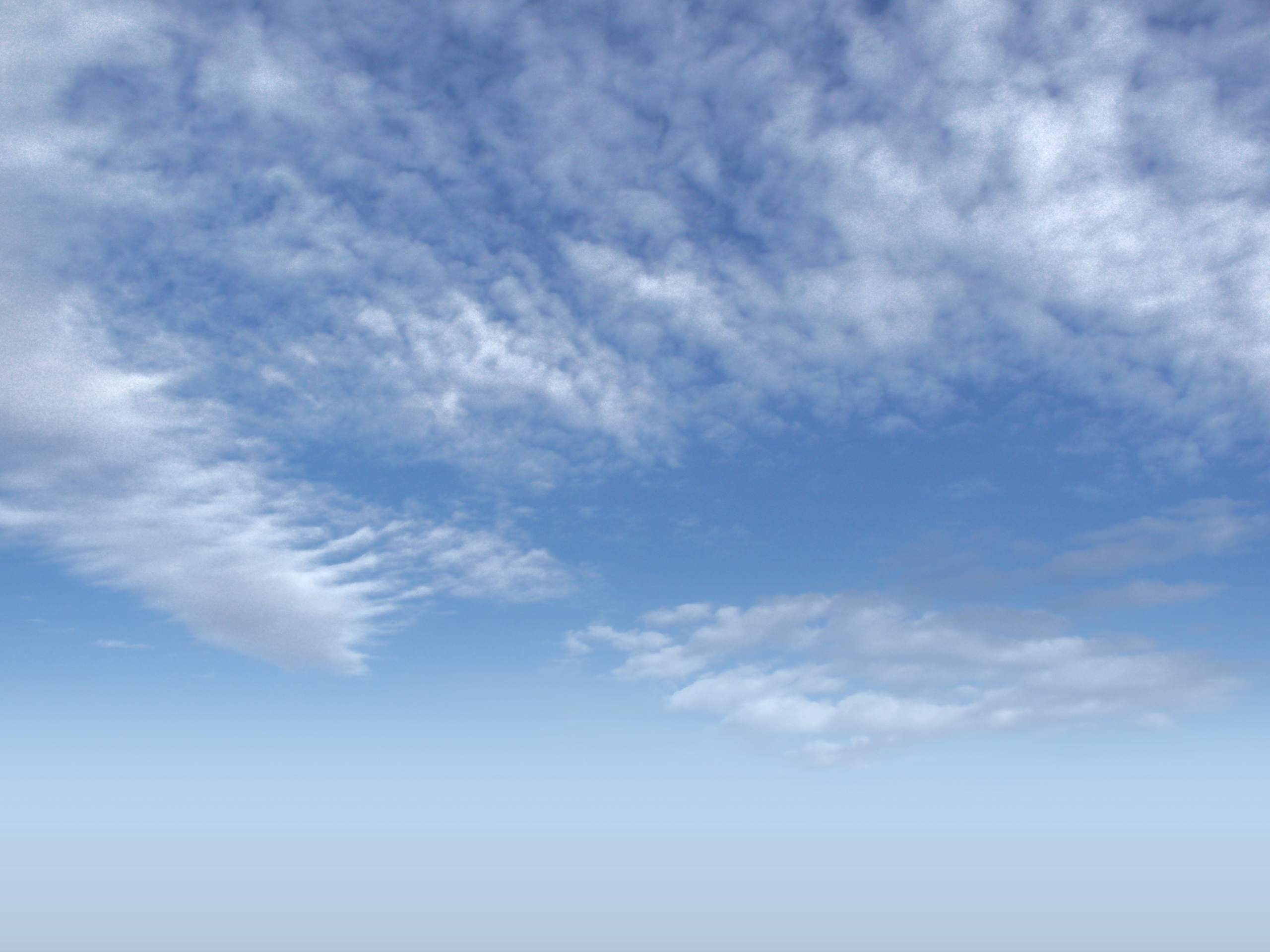
多くの飼い主さんにとって、愛猫は毎日見ていても飽きないほどかわいい存在でしょう。
ですがトイレ回りなど飼う上で困ることが多いのも猫の特徴です。
特にトイレ以外の場所で粗相をしてしまった場合の処理や、消臭方法など正解が分からず、疑問に思っている方も多いでしょう。
猫の粗相はストレスや病気など猫にとってのSOSでもあり、自分が猫に与えている環境を見直すきっかけにもなりますのでそちらの対策と共に、してしまった粗相の対処法などをご紹介したいと思います。
1.自分で出来る?猫のうんこの臭いを消す方法
猫は肉食性のため、うんこは強い臭いがします。
たとえ、トイレでしていても、どうしても
もしも猫のうんこの臭いで困った場合、こうしたでその方法をご紹介いたします。
(1)猫がトイレにしたうんこの臭いを消す方法
基本的に猫はトイレでうんこをしますので、臭い対策としてはトイレを清潔に保つことが基本です。
異臭を感じたら、すぐにトイレをチェックしてうんこをしていないかを確認する習慣をつけましょう。
もししていたらすぐに取り除き、密閉した容器や袋に詰めて処分するまで開けない様にします。
トイレに流せるタイプの猫砂であればすぐに流せます。トイレの近くに消臭剤を置くのも良いでしょう。
最近のトイレは密閉型や猫砂に消臭効果があるなど、臭い対策が施されているものが多くなりましたが、そういった対策をいくらしても臭ってくるのが猫のトイレ回りの臭いです。
こうしたトイレ回りの臭いを消すには、定期的にトイレ自体の洗浄が必要になります。
多くのトイレはプラスチック製ですが、表面などの細かい凹凸部分には臭いの元が残っていますので、しっかり落とすことが必要です。
猫砂も定期的に洗って天日干しなどをすれば、衛生的にも安心して使用できます。
(2)猫がトイレ以外にしたうんこの臭いを消す方法
猫は基本的にトイレで用を足しますが、トイレが汚れていたりなど気に入らない場合や別途ストレスを感じていると、トイレ以外の場所で粗相をしてしまうことがあります。
また多頭飼いの家庭ではトイレの数が足りず、粗相の原因ともなりますので、頭数+1個のトイレを用意することが一般的です。
こうした粗相の臭いは早めに対応しなければ、猫がそこを前にうんこをした場所=トイレと認識し、何度も繰り返してしまう要因となります。
そこでトイレ以外の場所でうんこをした場合は、すぐに洗濯するか消臭する必要があるのです。
粗相をしたものがカーテンや衣類など、洗濯できるものであればしてしまったうんこを取り除き、なるべく拭き取ったうえで酵素系洗剤を利用して急いで洗濯しましょう。
もし洗濯できないサイズ感のものであったり、洗濯することができない材質のものであれば、きれいに拭き取って消臭スプレーで消臭するか、熱湯などを活用すれば消臭できます。
2.臭いを抑える!猫のうんこの臭い対策を紹介
臭い対策としては猫のうんこの臭いを抑えたり、粗相の原因にもなるトイレを清潔保つなどの方法で対策をすることもできます。
対策1.便臭が抑えられる餌に変更する
猫のうんこの臭いの元になるものは、当然ながら毎日食べている食事、キャットフードになります。
キャットフードは各メーカーが様々な種類のものを出しており、この種類によって臭いが大きく変わったという経験をされた飼い主さんも多いことでしょう。
そこで臭いが気になるのであれば、猫のストレスにならなかったり体調を崩さない範囲でキャットフードを変更するという方法もあります。
ただし猫は非常にストレスを感じやすい生き物ですので、ちょっとした変化ですぐに体調を崩しがちです。
特に毎日楽しみにしているキャットフードが変わることは大きなストレスになり得ます。
もしキャットフードを変更する場合は、現在食べている種類のものからいきなり変更するのではなく、徐々に変えていくと良いでしょう。
最初は全体の1割ほどを新しいキャットフードにして、2割・3割と徐々に割合を増やしていく方法が猫にとってのストレスにならず、体調を見ながら行えるのでおススメです。
対策2.トイレで排泄が出来る環境を作る
猫は非常にきれい好きな生き物で、一般的にトイレにはこだわりがあります。
例えば多頭飼いで他の猫がした後は絶対にしなかったり、前に自分が使用したまま掃除がされていなかったらしたくても我慢するなど、知らず知らずのうちにトイレの環境がストレスとなっている場合が有るのです。
そのためトイレが汚れたままだとトイレを我慢しすぎて膀胱炎になったり、我慢しきれずトイレ以外の場所で粗相をしてしまうことになります。
一度粗相をした猫は、それが癖になってトイレがきれいになっても粗相を繰り返すことがあり、一度ついた癖はなかなか治らないので注意が必要です。
トイレの掃除はこまめに行い、定期的にトイレ自体も洗うなど清潔なトイレ環境を用意し、猫のストレスにならない工夫をしましょう。
3.どうして臭い?猫のうんこが臭い理由とは
強烈な臭いのある猫のうんこですが、その理由は食べ物にあります。
猫は人間と比べて約5倍のタンパク質を摂取する必要があり、市販のキャットフードなどもその様に栄養を調整されているのです。
排泄物の臭いの元は動物性タンパク質の量が大いに関係すると言われていますので、日頃からタンパク質の多い食事をしている猫のうんこは臭いのではないかと考えられます。
また、そもそもが臭いが強烈になりやすい猫のうんこがさらに臭う理由としては、体調面の悪化や餌があっていないなど、気を付けるべきサインの可能性もありますので注意が必要です。
理由1.食事の栄養バランスが乱れている
猫も人間と同様に、タンパク質や脂肪、炭水化物・ミネラル・ビタミンなどの栄養素を必要としています。
ですが本来肉食動物である猫は消化器官が体重全体のわずか3%程度と、多種多様な栄養素を大量に吸収出来るようにはできておらず、炭水化物や食物繊維を消化できる量は限られたものです。
そのため摂取する栄養素も必要とする割合は人間とは大きく異なり、これらの栄養素のほとんどを動物性の食品からとることに特化しています。
それに対して飼い主さんが手作りで食事を用意したり、猫がおやつなどばかりを偏食することで栄養が偏ってしまうと、栄養のバランスが崩れた状態になりうんこの臭いもより悪化したものになりがちです。
また、市販のキャットフードは基本的に猫に必要な栄養素のバランスを考慮して作られていますが、猫の年齢や生活環境によっても必要な栄養素も変わってきます。
そうした点を考慮し、猫にとっての最適な食事を用意するようにしましょう。
理由2.餌が身体に合っていない
タンパク質を人間より多く摂取する必要のある猫ですが、タンパク質を多く含むといっても肉や魚ではなく動物の血液や毛などを含んだ材料が主原料となった食べ物ものは消化されづらいとされ、臭いの元になることがあります。
また猫は穀物をうまく消化できないので、食べ物に穀類が使用されていることは腸内に溜まった穀類が発酵して便が臭くなる原因です。
消化不良を起こして臭いの原因になるだけでなくアレルギーの原因にもなりますので、猫に与える餌は穀物を使用していないものを選ぶと良いでしょう。
また食物繊維不足も臭いの原因ですので、もし気になるようであれば食物繊維が多めに含まれる毛玉ケア用のフードに変えるというのも一つの方法です。
食事で食物繊維を摂りすぎると、うんこが柔くなり下痢の原因にもなるので注意が必要ですが、便秘気味でうんこの臭いが気になる猫の場合は改善が見込めます。
理由3.餌の消化ができていない
例えば猫が牛乳を飲むと下痢をする場合が有りますが、これは猫には乳糖を分解する酵素の分泌が少ないことが多く、乳製品を与えると消化不良を起こしてしまう場合が有るからです。
この様にせっかく食事を食べたとしても、猫が消化吸収できるものでなければ消化不良を起こし、下痢などの大きな原因になってしまいます。
また普段であれば消化できるものでも、風邪をひいたりして体調が悪い時は消化できない状態となります。
人間もうんこの状態が下痢気味である時はそうでない時と明らかに臭いが違いますが、これは腸内のバランスが崩れ腸内細菌が増えて排出されたときの臭いです。
つまり消化不良が起きるとうんこの状態も変わり、臭いの大きな要因となってしまいます。
猫の毎日のうんこの状態なども確認して、下痢が起きているようでしたら消化不良を起こしている可能性が高くなりますので、食事などで猫が消化できないものをあげていないか、また体調面などに異変がないかの確認をしましょう。
理由4.ストレスがかかっている
猫はストレスに弱い動物ですので、環境や食事の変化、長時間の移動などにより体調を崩しやすくなりますし、季節の変化にも弱く、毎年季節の変わり目に体調を崩す猫もいます。
特に引っ越しなどによる環境の変化や新しい家族や、ペットが増えた場合などは慣れるまでは異常行動や下痢といった症状がみられるので、なるべくストレスの無い環境を用意してあげることと、もし環境に変化がある場合は、変化に慣れるまで注意深く接することが大切です。
こうしたストレスがかかっている状態が下痢などの原因になることもあるのでうんこが普段よりもより臭くなることがあります。
またストレスは粗相などの原因にもなるので、トイレ以外の場所でしてしまうこともあり得ることです。長く続く場合は動物病院に相談しましょう。
理由5.運動不足状態になっている
毎日長時間寝ているなど、部屋でゴロゴロしている時間が長い猫ですが、本来は野生で食うや食わずを生きる動物ですので、十分すぎる程の食事にありつけ、かつ安全な室内飼いでは運動不足による肥満気味な猫が多いようです。
運動不足は筋肉の衰えのほか体内の働きも低下してしまう傾向が強く病気の原因にもなりますし消化不良や食欲不振からうんこの臭いの悪化へも繋がっていきます。
なるべく毎日時間を作って猫と遊んであげて運動不足を解消してあげましょう。
体力や年齢、猫種にもよりますが、1日2回以上、1回10分を目安に遊んであげるのがベストとされ、時間が無ければ1回5分程度でも構いませんので毎日何回かに分けて遊んであげると良いでしょう。
4.【事例あり】猫のうんこの臭いを消しきれなかったら業者に頼もう!
ただでさえ臭いがきつい猫のうんこですが、状況によってはさらに強烈な臭いになり十分な臭い対策をしていたとしても部屋や家具などに移ってしまうことも十分にあり得ます。
そうして家に移ってしまった臭いは、その家に住む方にとっては“当たり前”になってしまい、なかなか異変に気付くことができない点も厄介なポイントです。
個人での対応には限界がありますので、長期間猫を飼われていたり、直近で粗相をしてしまったなどの場合はやはりプロに頼むのがベストでしょう。
一般には販売されていない薬剤や機材を使用すれば、厄介な猫のうんこの臭いにも対応できます。
事例1.ペットが糞尿を散らかした部屋の清掃
飼い主さんが長期間不在にすることは、猫にとってもストレスな環境となり、思わぬ異常行動に出ることもあります。
こちらは特殊清掃を専門に行っているブルークリーンという会社が過去の事例としてHPで紹介している例なのですが、
室内飼いでペットを飼っている依頼者さんは、仕事の出張中に友人に飼い猫の世話を任せていたところ、帰ってきたら室内が糞尿で散らかっていた為連絡したとのことです。
状況としては部屋全体に糞や尿が散乱し強烈な悪臭を放っており、糞尿以外にもエサや生ゴミが散らかっていた為強烈な悪臭が室内には充満しており、とてもではありませんが個人で対応できる範囲を超えており、急いで対応する必要がありました。
対策として
- 腐敗物の撤去
- 除菌消臭
- 脱臭
- 整理整頓
- ハウスクリーニング
をブルークリーン社が行い、事なきを得たとのことです。
間取り | 1K |
|---|---|
作業時間 | 3時間 |
作業人数 | 2名 |
作業費用 | 122,000円 |
事例2.ペットの糞尿が放置された部屋の片付け
こちらの事例では、ご病気になり亡くなったご家族の遺品整理がでなかった依頼者さんの事例です。
ご依頼の家は築20~30年以上の二階建ての一軒家で、ペットとして猫を飼っており、部屋に排泄物が散らばったままで臭いも強く、遺品整理と共にハウスクリーニングも必要な状況だったとのことです。
部屋数が多く片付ける物量も多く、糞尿が廊下まで散乱しているという状況で除菌や臭い対策も必要でしたが、片付けと糞尿の清掃を含めたハウスクリーニング、脱臭を同時におこなうこができた、ということでやはりプロの技が光った事例と言えるのではないでしょうか
間取り | 戸建て |
|---|---|
作業時間 | 2日 |
作業人数 | 4名 |
作業費用 | 462,000円 |
まとめ
猫と過ごす毎日は至福の時間ですが、同時に食事やトイレなど気を配らなければならないものも数多く発生します。
猫が粗相をしてしまうのは、それら飼い主さんが気を配らなければならないことで何かしらの問題が発生している可能性があり、飼育している環境を見直す必要があるのかもしれません。
飼育環境を見直すきっかけにするとともに、起きてしまった粗相には早急に対応し、二次被害三次被害が起きないよう対応していくことが大切です。

監修者AOAO研究員(すーさん)
これまでブルークリーン㈱で数々の特殊清掃や遺品整理などを見てきた経験から、
AOAOで記事の監修を行っています。